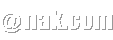三台目:Thinkpad X20 CPU-Pentium III 600Mhz,memory 256MB,HDD 20GB
1998年後半から約2年間SonyのVaioシリーズに「浮気」していた当方が、21世紀を迎えるにあたり
仕事用のマシンとして選んだのがX20である。
ビジネスユースモデルとして設定されているX20は個人ユースモデルであるThinkpad i1620とは
いわば兄弟モデルである。i1620に装備されているIEEE1394の代わりに100baseTが装備されている他、
CPUの選択肢としてPentium III 600Mhzが用意されている。
外出等NotePCを持ち歩く機会が多い身として携帯性を重視する一方で、携帯用マシンとして
使っていたVaio C1では携帯性を追求する余り液晶画面が小さい(縦方向)、キーピッチが狭い
という点でストレスを感じる、という経験もした。(C1は実は余り軽くなかった、という事も知った。)
そしてやはりPCには何よりも信頼性を追及したい、という気持ちが再度起こったのである。
・・・やはりIBM以外のマシンではパソコンとしての信頼性がイマイチ得られなかった。
要はブルースクリーン、ソフトパワーオフせず、ドライバサポートが貧弱・・・色々苦労があったのである。
よって今回は自ずとIBM Thinkpad....サイズは最低でもB5サイズ以上、一応携帯性も考慮、そして
少なくとも2,3年はストレスなく使用できるCPUパフォーマンス...そういうマシンを求めた結果、
X20という選択になったのである。

普段は我がデスク上でいわばサブ・デスクトップとしてCDROM,FDD等周辺機器を接続して使用されつつ
会議出席、そして外出時に持ち歩く用途として使うノートPCの場合、携帯時には必要最低限の形態で持ち歩く
事が出来(=CDROM,FDDといったものは不要)、携帯時にはそういった周辺機器が簡単に(すばやく)
脱着可能である、ということが重要になる。
X20を選んだ理由の一つにはUltraBay2000の存在がある。これはいわゆるFDD、CD-ROM(CD-R/W,DVD-ROM等に付け替え可能)、
シリアル、パラレルポートが備わったdocking stationである。


机の上ではこのUltraBay2000にドッキングされたX20がフルI/Oマシンとして動作する一方、X20を持ち運ぶ際には
ボタン一つでUltraBay 2000から脱着出来るのである・・・電源が入ったままで。これは便利である。
(小生がそういう「仕掛け」がスキ、という事もあるのであるが・・・)
1024*748の液晶の大きさに感激しつつ、B5”ファイル”サイズの大きさには最初若干戸惑った
(もう少し小さくてもいいかな、と)ものの、Thinkpadのキーピッチ、キータッチ、そしてTrackpointの
良さを再認識しつつThinkpadder復活!
01/02/01...New machine->Win2000 upgrade !
当方が入手したX20はWindows98SEがプレインストールされたモデル。
当時のノートPCは殆どWindows MEがプレインストールされていた事を考えるとちょっと異質。
しかし同じhardwareでもWindows 2000がプレインストールされたモデルは20000円高との事。
ここは節約。その分、周辺オプションとして同時に↑に書いたUltrabay 2000とCDROMドライブを入手。
で、何を真っ先にやったかというと・・・
Windows 2000へのupgrade.....
さすがIBM....X20のWindows 2000用デバイスドライバ、ユーティリティが全てIBMのサイトからダウンロード出来る様に
なっている。
- Display driver
- Sound driver
- LAN driver
- Thinkpad Utilitiy
Win2000へのupgrade後、X20はすこぶる好調。
01/02/16...LINUX on X20
X20に搭載の20GBのHDDをPartition Magicを使って2分割してLinuxをインストール。
使用ディストリビューションはRed Hat Linux 7J。PCMCIAサポートを含めて
ドライバサポートは充実しておりノートPCに適したディストリビューションである。
Linux自体のインストールは問題なく終了したのであるが、リブートするもなかなかLinuxが
ブートしない。
Linuxのインストールパーティションに一工夫が必要なのである。
すなわち大概のOSの場合、HDDの先頭8GBにブートエリアが配置されることが必要であり
Linuxも標準インストールモードではその例外ではないのである。
Windows2000のパーティションを移動、分割してLinuxのBoot領域を先頭8GBに設ける
という「大手術」を敢行するしかないか、と諦めかけながらRed Hatのマニュアルを
再度眺めていると・・・あった・・・
8GB超の領域にブートエリアを配置するインストールモード。これにより先頭シリンダに関係なく任意の
パーティションにLinuxのカーネルを配置できる。
このモードでインストールを行なった結果無事Windows 2000/Red Hat Linux 7Jのダブルブート成功。
TCPIPの設定も行ないNetscape NavigatorでWeb browsingも無事にできた。
さて、本機を使用して2ヶ月目のインプレッションであるが、
- キーボードのタッチが秀逸。....キーストロークの深さもさることながら独特ともいえる
やわらかくかつ確実なタッチがいい。このタッチは昔のThinkpadから伝統的とも思われ
自分にとってどこか懐かしい。
- 外装がデリケート!?....手垢がすぐついてしまうマグネシウムめっきのLCDカバー。またカバン、
デーパックに入れて運んだ結果エッジ部分のメッキが一部剥がれた。
- Port replicator装備のIOポートと本体装備のIOポート....Port replicatorに本体を装着時には
ACアダプタはreplicatorに接続してreplicator経由で給電する形態になっている。ところが本体に
装備されるIOポートは全て本体のポートをそのまま使用する・・・すなわちrelicator側にコネクタ
がないのである。
replicator使用時、すなわちデスクトップにて使用する状態で使う周辺機器、
USBやLANはreplicatorに接続しておきたいものである。replicatorから本体を外したときに
毎回ケーブルを外す面倒なことは出来れば避けたい・・・そういう作りのreplicatorが欲しいものである。
01/04/25...Bulti-boot on X20
3月に海外出張へX20を携帯。
海外からのインターネットアクセスは何ら問題無し、すなわちモデムの相性はすこぶる好調。
ACアウトレットのない会場でのバッテリー駆動も思いの外長時間可能で、スペアで購入した
バッテリーパックと合わせて2本でほぼ一日バッテリ駆動が可能であった。
今回の出張に際し、社外から社内イントラネットへアクセスするためのソフトが
Windows 98用しかなかった為に仕方なくWindows 98をインストールするはめに。
簡単に装換可能なHDDを標準搭載のものからTOSHIBA製の20GB品に交換。動作音が
IBMのもの(標準搭載品)よりずいぶん静かである。そのHDDにまずはPre-install用CDROMで
Windows98SE+プレインストールソフトを製品インストール状態にセットアップ。
イントラアクセスソフト(そう、VPNです。)の動作確認を行なった後に、
Windows 2000をインストール。cドライブにWin98SE, dドライブにWindows2000という
構成に。
その後、前回同様Partition Magicを使って2分割してLinuxをインストール。
Win98/Win2000/Linuxの3OSマルチブート環境が出来あがった。
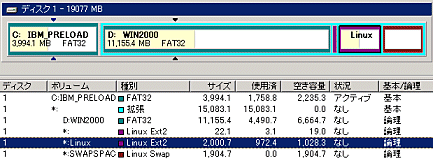
前回X20のインプレッションとしてreplicatorの出来の中途半端さ(relicator側にコネクタ
がないので本体携帯時のケーブル類の取り外しが面倒である)を挙げたが、
先週SonyのVaio 505 seriesの新モデルとしてVaio PCG-R505が発売された。A5ファイルサイズの
Pentium IIIマシンという事でX20と競合する仕様のモデルである。
この機種にはX20同様Docking Stationが用意されているのであるが、全てのIOコネクタを
Docking側に持っているのである。ドッキングに装着されている状態では当然の事ながら
Docking Station側のコネクタ類が有効になる、ステーションから脱着すると本体側のIOが有効になる、
という代物である。本来Docking Sattionとはそうあるべきものであると思う。
それにしてもVaio PCG-719をはじめX20、そしてVaio PCG-R505、昔ではApple DUOとDocking Station
が好きなのである。